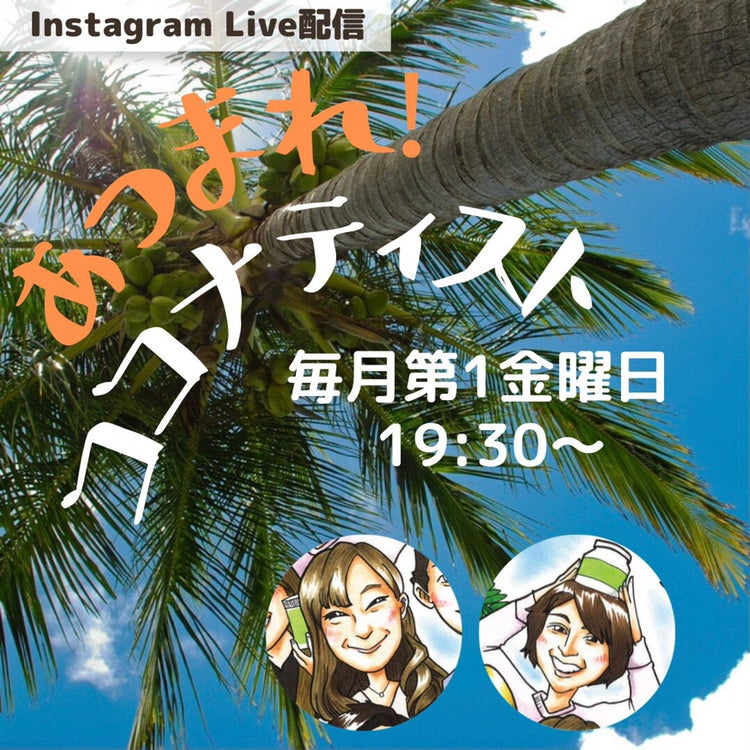フィリピンで食べられているバナナの品種
フィリピンで消費されているバナナは、ラカタン、ラトゥダン、サバ(調理用)、セニョリータバナナ(モンキーバナナ)などと呼ばれる品種で、日本に輸入されているものとは異なります。
日本に輸入されるバナナとその変遷
日本に輸入されるバナナは1950年代まではグロスミッチェルという品種でしたが、パナマ病により壊滅的な被害を受け、現在ではパナマ病に耐性を持つキャベンディッシュが大部分を占めています。日本のスーパーで見かけるバナナはほぼすべてがこのキャベンディッシュという品種になります。
逆にフィリピンの市場ではこのキャベンディッシュを見かけることはほぼありません。
バナナの種と増え方の仕組み
現在私たちが食べているバナナには種はありませんが、元々原種には大きな種がありました。突然変異で種無しのバナナができ、現在のバナナはその突然変異の種無しバナナを株分けすることで増産されています。茎の脇に出てくる新芽を苗にして育てる仕組みです。果肉の黒い点は、種があった名残です。
遺伝的なリスクと病害の影響
現在のバナナは株分けによって生産されているため、すべて同じ遺伝子を持っています。同じ遺伝子の方が効率的ではありますが、この遺伝的画一性により、一たび抗体のない病原菌が発生すると甚大な影響を受けてしまいます。
グロスミッチェルがキャベンディッシュに置き換わったのも、グロスミッチェルがパナマ病の蔓延で一瞬にして壊滅的な被害を受けたことが原因でした。
現在のキャベンディッシュはパナマ病には耐性がありますが、新しい菌による影響を完全に防ぐことはできません。数年前には南米のコロンビアで「新パナマ病」と呼ばれる真菌が確認され、キャベンディッシュに大きな被害が出たことがあります。
バナナ栽培と農薬の実情
普段私たちが食しているバナナは、病気への感染を防ぐために農薬が大量に使用されています。一部では今でも飛行機による空中散布も行われていると言われています。